書籍情報
書籍名:ニュートン 科学の学校シリーズ 心理学の学校
発行所:株式会社ニュートンプレス
 | ニュートン科学の学校シリーズ 心理学の学校 [ 横田正夫 ] 価格:1540円 |
読書理由
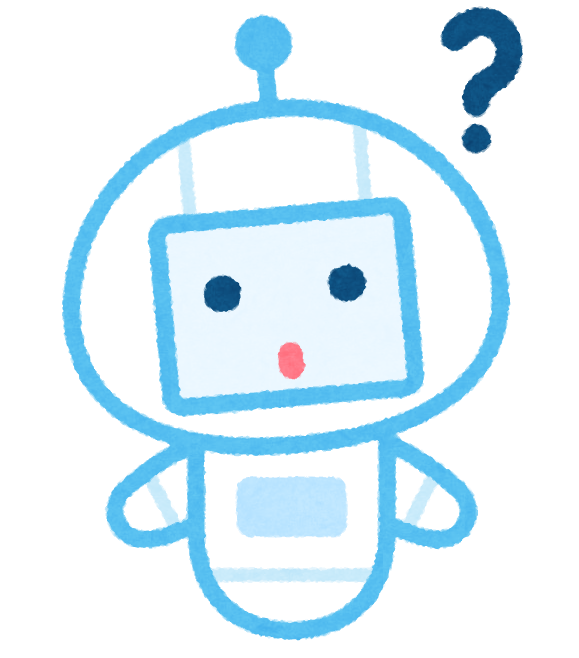
心理学の本をなぜ読もうと思ったの?

前から心理学ってどんな感じなんかなーってちょっと興味があり、「ちょっち心理学の本読んでみっか!」ってな感じです!
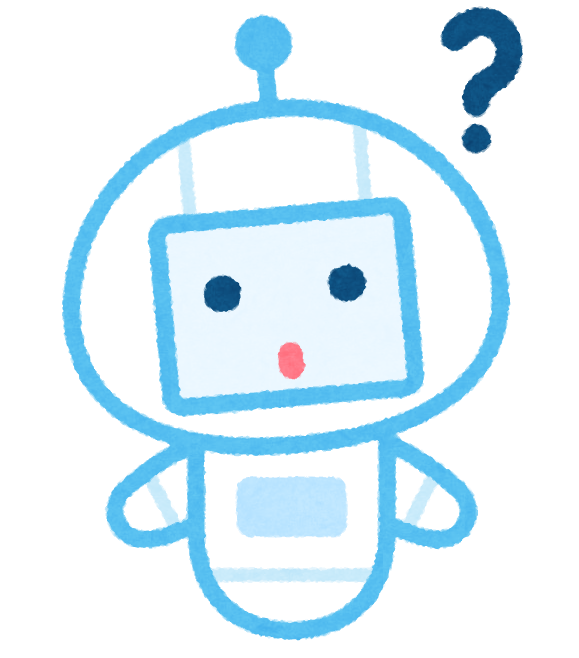
心理学の本はたくさんあるけどなぜこの本?

高度な専門書だと確実に途中で心が折れると過去の経験でわかっていたので…児童書から選びました。
備忘録
感想
本書では、
- 心理学ってどんな学問?どんなことしてるの?
- 人の心ってなに?
- 心理学で何ができる?
- 日常の出来事と心理学の関係
などなどについてわかりやすく書かれている。
今の自分の分析、家族との関わり、周囲の人、モノとの接し方を考える上で役に立ちそう。
児童書を読んだことがなかったが、しっかりとした内容で驚いている。
児童書ではあるが、大人にとっても学びがあると思った。
今後は、初めて学ぶことやあまり詳しくないことを学ぶときは児童書も活用していきたい。
メモしておきたいこと
本書でメモしておきたいことは以下のとおり。
子どもの心の発達と大人の心の発達
心の発達に関して記載されていたことは以下のとおり。
1つ目は、「子どもの心の発達は4つのステージを経て成長する」というスイスの心理学者ジャン・ピアジェの理論だ。
子育て中の私としては、しっかりと理解しておきたい。
2つ目は、「大人になっても心の発達は続き、生涯での心の発達は8つの段階があり、各段階で危機とそれを解決するための課題がある」というアメリカの心理学者エリク・H・エリクソンの理論。
現在の年齢付近の段階を見ると、確かに…という感じ。
まだ先ではあるが、60歳を過ぎると自分の人生に後悔し「絶望」する「危機」が訪れ、それを解決するためには、人生を肯定的に受け入れる「統合性」を得る「課題」をこなす、とのことだ。
これまで歩んだ各段階の「危機」と「課題」を見ると、恐らく避けては通れなさそうなので、心構えとして覚えておきたい。
1つ目の理論だけでなく2つ目の理論も、子育てにおいて子供がこれからどういう「危機」を迎えどう「課題」を解決するのかを知っておくと役に立ちそうな気がする。
2つ目の理論における、アイデンティティを確立する「青年期(所謂、思春期)」について、臨床発達心理学者のジェームス・マーシャのアイデンティティ確立のタイプ分けを引き合いにし詳しく紹介されていた。
自分で自身に問い、考え、答えを見つけ出すことが最も安定するらしい。
アイデンティティ確立については、思春期以降も付き合うことになると思うが、自分で答えを見つけ出すことの難しさを現在進行形で感じている。
セルフ・ハンディキャッピング
自尊心を守るために無意識に失敗しやすくなるような行動のこと。
どのような行動かというと、失敗した時に自尊心を守るための言い訳ができるような不要な行動(試験前日に部屋の掃除とか)をとることや、「今日調子悪いのよね~」「全然勉強してね~」などをわざわざ周囲に言い失敗に備えることなど。
学生の頃、こういう人周りに絶対いたし、自分もしてた。
やり続けると、向上心や挑戦心に影響あるので、気を付けたい。
集団同士の対立
複数の集団があると原因がなくとも対立することがある。
対立を解消し仲良くするには、共通の目的をもたせるとよい。
対立解消をする機会は、今のところないし、共通の目的だけでは難しいと思うが、そういう実験結果があるという事実は覚えておきたい。
認知のゆがみ
物事を判断する際、ストレスにつながるような判断の仕方をする癖がある。
それを認知のゆがみと言う。
いくつかの例が紹介されており、私にも当てはまることがいくつかあった。
認知のゆがみが出たら、意識して再考するようにしたい。
自己概念と経験的自己
自己概念は「自分が考える自分自身」、経験的自己は「実際の体験に基づく自分自身」であり、この2つが重なっているほどストレスが少なく心が安定している。
反対に重なりが少ないと、強いストレスになる。
自己分析して重なる領域を増やしていきたい。
ほめてのばす
「ほめてのばす」は、よく耳にするが、心理学として正解。
子育てに役立てよう。
フレーミング効果
内容は同じでも表現により答えが変わる。
仕事で使えそう。
